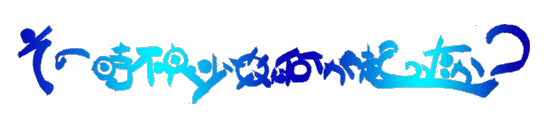
3話「繋」
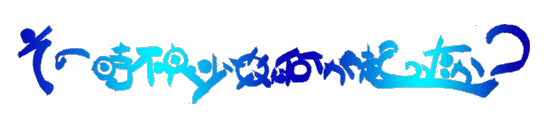
3話「繋」
「まったく、使った玩具を片付けるって事も知らないのかな」
人通りの無い神社の境内にゆっくりと夜の帳が降りて来てあたりを闇に包み込む、街灯の灯が淡い光で申し訳程度に大地を照らす頃、うち捨てられた皐月の身体が白く光って見えた。
「こんなとこで寝てたら風邪引くよ」
やって来た正史はそのあまりにも惨く悲惨な状態の皐月を居間で酔いつぶれて寝てしまった父親でも起すように揺さぶった。
「起きないな? よほど疲れてるんだね」
天使の微笑みで笑いかけるとサイドバックから何か取り出すと皐月に押し当てて……
バチッ!!!
「ぎゃっ!」
バチッ!!
「ぎゃぁ!」
バチッ!
「ぎゃ……」
スタンガンを三度使ってみせた……
「起きた? 呼んでるんだから返事しなきゃダメだよ……学校で習わなかったかな? 挨拶は大切ですって」
なにが起ったかわからない皐月は全身がぴくぴくと痙攣していることにただただ恐怖していた。
「あ……な……な……なに……を……」
バチッ!!
「ぎゃあああ」
「はっきり言いなよ……なってないな君は……」
目の前にいる正史が何者でそして今が……どういう状況なのか皐月にも理解出来た……そして、さらに恐怖が増していた。
「いやぁ……もう帰して……うちに帰して……お願い……いやあ……」
皐月の言葉を聞いているのか、正史は皐月の股間を点検するように陰毛をしゃりしゃりといじっていた。
「玩具に傷をつけるなんてあいつ等もわかってないね、玩具は大切に使わないとすぐ壊れちゃうのに」
「お願い……帰して……縄を解いて……きゃあ!」
もう一度スタンガンを押し当てると皐月の方を向いて。
「あのマンションかい? いい所に住んでるよね……部屋もけっこう広いしさ、防音もばっちり……沢山の人が騒いでも近所に迷惑にならないもんね……」
皐月は正史の笑顔の視線に耐えられなくなった……そして
「なんで……私の家を……知って……」
恐怖は嫌がうえにも増して来る。
「なんでって……何でだと思う?……今は内緒だよ……ククク……じゃあ行こうか?」
正史は皐月の首に犬の首輪をつけると引きずるように外へと歩き出す……
「いやあ、このままなんて外へ行けないよ……裸なのよ……お願いゆるしてぇ」
既にこのあたりで名を轟かせた皐月の面影は無く、ただ凌辱に翻弄されてなく事しか出来ない娘が一人そこには居るだけだった。
皐月の言葉に正史は気を悪くしたでも無く。
「しょうがないな……」
神社の入口にある鳥居の裾に首輪からつながる紐を括り付けると
「じゃあぼくは帰るから……」
そう言って神社の前の階段を降りて行こうとする……
「うそ……こんな所に……うそ……」
皐月の視界からどんどん小さくなる正史の背中は一回も振り向かずに消えていこうとしていた、この場所に置いていかれる……それも犬のように……
「まって……置いていかないで……ここに残るのはいやあ……」
正史の背中に向かって助けを求めていた……
「まってよ……」
その声に天使の微笑みで振り向く正史は……
「言葉遣いはちゃんとしようよ、君とぼくどっちが主人なのかな? いくら君が馬鹿な女子○生でもそれくらいの分別はあるよね?」
しかし瞳は笑っていないで皐月を威圧している。
「わからないの……馬鹿だな君は……それとも現代の学校教育って根本から間違ってるのかなぁ……まず言い方は、待って下さいでしょ? そしてここに残るのは嫌ですから連れていって下さいお願いします、ご主人様、ここまで言ってくれなくちゃね」
あまりの言葉に皐月はただその場で肩を震わせて
「そんな事……」
「言えないならいいよ、朝までそこに居れば? やさしい誰かが拾ってくれるかもよ、あ……そうそう工藤君の朝のランニングコースだよねここ……きっと工藤君が見付けて拾ってくれるよ」
笑顔のまま正史は階段を降りて行く。
「待って! ください…… ここ……に……残るのは……嫌ですから……連れて……行って……下さい………………ごしゅ……じん……さ……ま」

|
両目からポロポロと涙を流して血を吐くような思いでそこまで口にした皐月の前に気がつくと正史が戻って来て立っていた。
「よく言えたね、恥知らずな女だね、君」
「!」
何かしら文句の一つも言いそうになる皐月の目の前にスタンガンがにゅっと指し出され
「さっきは電圧も一番低い奴だったけど、電圧上げたの何回もあびたら心臓が止っちゃう事もあるんだって……どうする?」
うなだれるしか無かった、もう皐月は目の前の少年の呪縛を解く気力を持ちあわせてはいない、今はこの少年の加虐がおさまるのを首を縮めてて台風が通り過ぎるのを待つように待たねばならないと痛む胸とそして股間で理解していた。
その様子に満足げに紐を解くと再び皐月を引っ張って歩き出した。
「前にペットを飼っててね……死んじゃったんだ……悲しかったな……この首輪はねその時使ってたやつだよ、よかったぺスが帰って来たみたいだ……」
上機嫌で正史は夜の住宅街を歩いて行く、既に遅い時間らしくどこの家も明かりはついているものの通りに人影は無かった。
「そう言えば、交尾したままだね妊娠しないようにするのも飼い主の勤めだね、洗っておかないと……」
そう言いながら住宅街の中にある公園へと皐月を連れて入っていく。
「ここ、さんぽコースだったんだ……」
夜、広い公園に人影は無くひっそりとしていた、風の音と遠くから民家のTVから出る笑い声だけが聞こえていた……しかしそれがこれから起るであろう凌辱劇への静かなる序曲であることは皐月にだってわかった、ただそれが彼女の想像をはるかに越えていることはこの直後に思い知る事になるのだった。
わかっていても涙が頬を伝って落ちた……